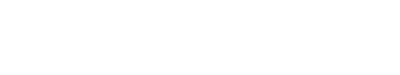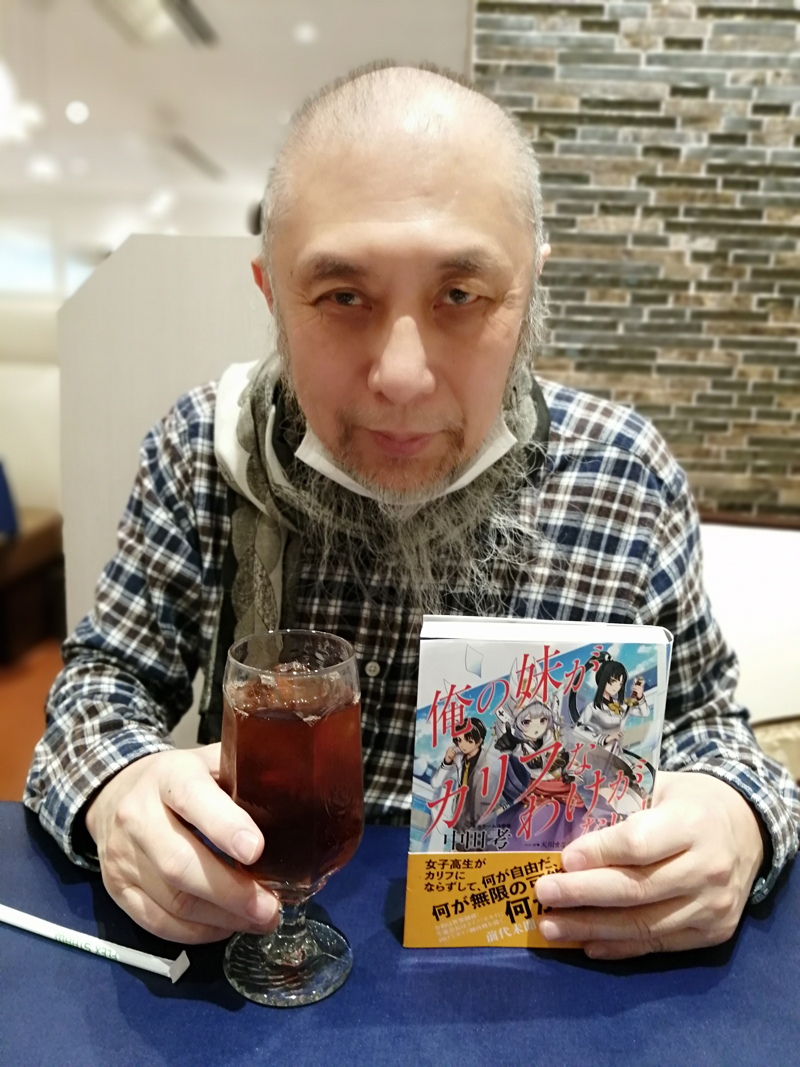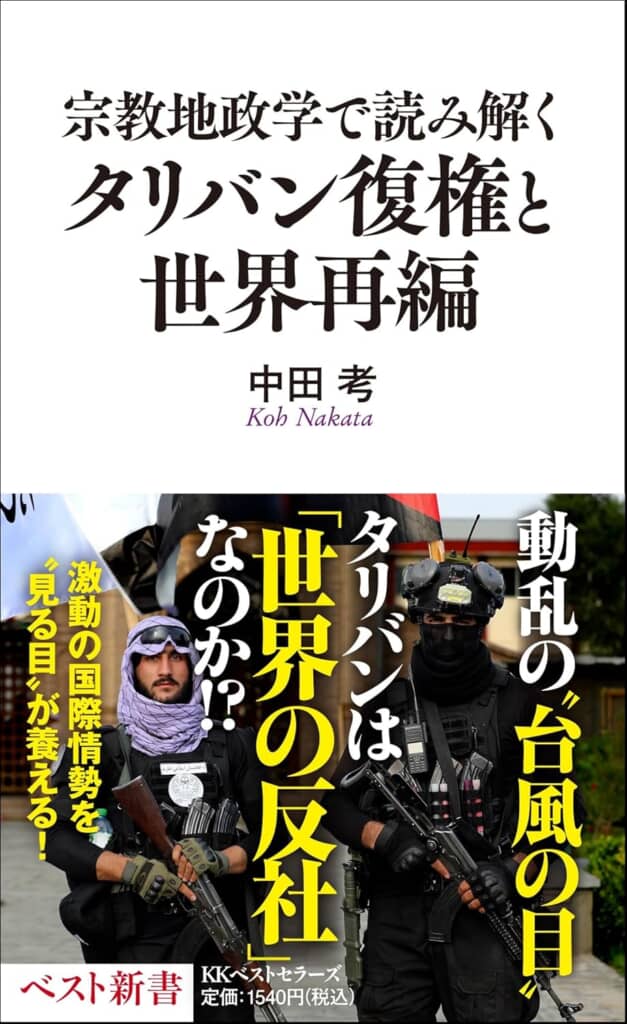【高市早苗】新総理に待ち受ける冷徹な現実。「対中抑止の最前線に立つ地政学的緩衝国家」としての役割【中田考】
《中田考 時評》文明史の中の“帝国日本”の運命【第2回】
◾️7.結語
2025年10月21/22日に読売新聞社が実施した全国世論調査によると高市政権に対して「優先して取り組んでほしい政策や課題」として最も多く挙げられた(複数回答可)のは物価高対策(92%)であり、リアルポリティクスにおいて最も国民の関心を引く問題は経済問題だろう。
しかし今日の世界は緊密につながっており、国際的なサプライチェーンの維持は経済に大きな影響を与える国民生活に直結する問題である。特に天然資源の自給率が12.6%(天然エネルギー庁2022年)、食料自給率(カロリーベース)が38%(農林水産省2025年)しかない“帝国日本”にとって外交は死活的重要性を有する。大日本帝国が無謀な大東亜戦争に突き進んだのも富国強兵政策の一環として海外に資源を求めざるをえなくなったからである。
そして外交は決して経済的合理性による利害損得の計算だけで動くわけではない。本稿で扱っただけでも、創価学会・公明党、統一教会、靖国神社などの「宗教」が外交の大きな争点になっている。しかし私見によると、これらの「宗教問題」を理解するにあたって、「仏教」、「キリスト教」、「神道」などの西欧的な宗教学の概念枠組みにおける定義と分類に従って、それぞれの教団の信徒についてその教義を参照して政治行動の分析を行うことはかえって問題の本質を見誤らせるものでしかない。特に歴史的に儒仏道の三教合一が人口に膾炙していた中華文化圏、東アジア、仏教、神道、儒教が社会空間においても一個人の中においても共存、混淆が常態であった日本においてはそれらの「宗教」は分析概念として役に立たない。
E.デュルケームとM.ヴェーバーは社会学の祖とも呼ばれる。前者は「人間は人間に対して神になった」(デュルケーム『個人主義と知識人』)、「(現代の道徳は)人間を信徒とし、同時に神ともする宗教」(デュルケーム『個人主義と知識人』)、後者は西欧近代の価値観の相違をめぐって人々が争う時代精神を「神々の闘争」(ヴェーバー『職業としての科学』)と診断している。しかし動植物は言うまでもなく木石までが神として祀られる日本においては、人間が神となることなど取り立てて言うまでもない、誰もが当然視している些末事でしかない。
東アジアや日本が世俗化において西欧より進んでいた、などということを言いたいわけではない。またグローバル化が進んだ現代においては東アジアだけでなく世界中で諸宗教が混交しさまざまな宗教の信徒たちが共存していることを「人神の多神教」と呼べばそれで現代の宗教状況を把握できると考えているわけでもない。
筆者は現代の資本主義社会における主神はリヴァイアサン(国家)、その配偶神はマモン(銭神)だと考えている。しかし現代における神々は、リヴァイアサンとマモンだけではない。日本神話では「八百万神」とも言われるように何もかもが神となり、その数に限りはない。八百万の神々がいると言っても、誰もその総体を知る者はなく、それらの神々が全て崇められているわけではない。
宗教学には「交替一神教(henotheism, kathenotheism)」という概念がある。多くの神々が知られており、ある時点ではその中の一柱の神を崇拝されるが、時に応じて崇拝される神が換わっていくという信仰形態のことである。人の意識は移ろいゆくものであり、一度に意識できる志向対象は限られている。その意味では、交替一神教とはむしろ多神教の常態とも言える。
現代人の主神がリヴァイアサン(国家)だとしても、人々が日常生活において常にリヴァイアサンを崇拝しているわけではない。人は日常においてはマモン(銭神)や自分の地位、仕事、見栄、家族、趣味、欲望などの神々に目移りしながらその時々にそれらのどれかを奉って生きている。交替一神教としての多神教には総体としてみた場合も、個々の成員を取り上げても、一貫性も整合性もない。それが多神教であり、現代世界の実相であるというのが本連載における筆者の立場となる。
リヴァイアサンを主神、マモンを配偶神とする人神の多神教が現代世界の宗教の実相であり、そしてそれを「交替一神教」として捉え直すことが、現代の人類社会の動態を分析する上で有効だと筆者は信じているが、交替一神教の概念を用いた分析は具体的な事例に即して次回以降の時評において適宜行っていくことにしたい。